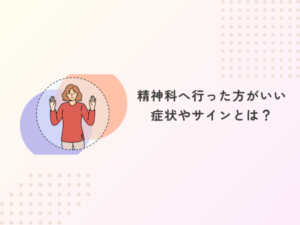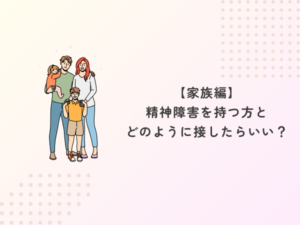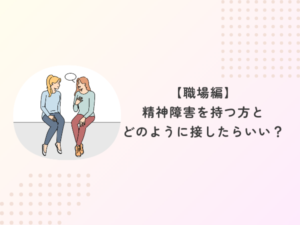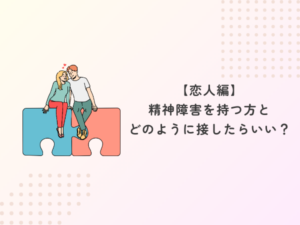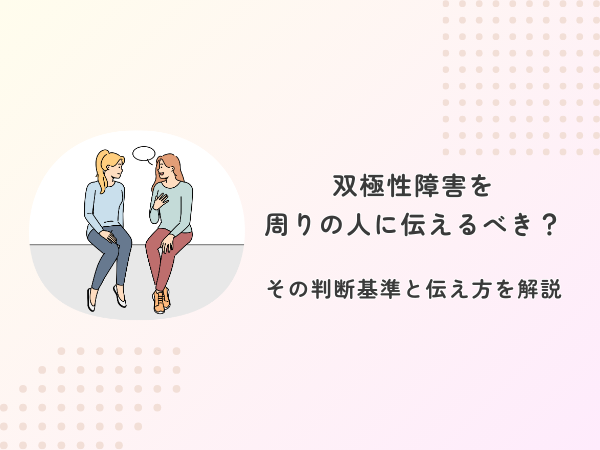
双極性障害は、気分が高まる「躁状態」と落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神障がいです。
以前は「躁うつ病」と呼ばれていました。
双極性障害を発症したことを周りの人に伝えられず、不安やストレスを感じたという方も少なくないでしょう。
そこで、本記事では双極性障害を周りに伝えるべきかどうかの判断基準と、周りの人へ双極性障害のことを打ち明けるときの伝え方を紹介します。
Contents
双極性障害とは

双極性障害は、気分が高揚する躁状態と、落ち込むうつ状態を繰り返す精神障がいです。
躁状態では、過度の活動性や高揚感が見られ、うつ状態では、抑うつ気分や興味の喪失が見られます。
医療法人社団 緑会によると、双極性障害の有症率は、0.4〜0.7%とされています。
双極性障害の診断基準
精神障がいの診断には、さまざまな基準が設定されています。
DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)も診断基準のひとつです。
DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)は、米国精神医学会が出版している書籍です。
DSMの最新版である「DSM-5」では、双極性障害を「双極I型障害」と「双極II障害」に分類し、以下のように定義しています。
双極I型障害
- 躁病エピソード(軽躁病/抑うつエピソードの前後に起こる)が存在する。
双極II障害
- 連続した4日間の軽躁病エピソード+2週間の抑うつエピソードが少なくとも1回存在する。
- 躁病エピソードは存在しない。
- 軽躁病エピソードでは、躁病エピソードで起こるような大きな問題(例:逮捕、対人関係の破綻、解雇)は生じない。
症状
双極性障害では、下記のような症状が少なくとも1週間、ほぼ毎日、持続的に異常な高揚、開放的、または易怒的な気分が続きます。
- 自尊心の肥大・誇大
- 睡眠欲求の減少
- 普段より多弁・しゃべり続けようとする切迫感
- 観念奔逸・考えが次々と浮かぶ感覚
- 注意散漫
- 目標志向性の活動増加・精神運動焦燥
- 結果を考えない快楽的活動への没頭(例: 無謀な買い物、性的逸脱、危険な投資)
双極性障害を周りに伝えるべきかどうかの判断基準

ここからは、双極性障害を周りに伝えるべきかどうかの判断基準を3つ紹介します。
- 仕事や学業、私生活に支障が出そう
- 大切な人との関係に影響が出そう
- 治療を始めた
仕事や学業、私生活に支障が出そう
双極性障害の影響で仕事や学業、私生活に支障が出そうになったら、周囲に自分が双極性障害であることを伝えましょう。
仕事や学業、私生活に支障が出そうなときに双極性障害を周囲に伝えることで、必要な配慮やサポートを受けられます。
また、周囲が症状を認識していることで、適切なコミュニケーションや支援が可能になり、自分自身の負担を軽減したり、治療環境を整えたりできます。
大切な人との関係に影響が出そう
双極性障害により家族やパートナー、友人との関係性に支障をきたしそうになったら、周囲に自分が双極性障害であることを伝えましょう。
大切な人との関係に影響が出そうなときに双極性障害を伝えることで、誤解や摩擦を減らし、信頼関係を維持しやすくなります。
また、オープンに話すことで、隠すストレスが軽減され、精神的な負担が軽くなります。
双極性障害の人が恋愛で気を付けるポイントについて知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
治療を始めた
双極性障害の治療を始めたタイミングも、周囲に自分が双極性障害であることを伝えるのに最適です。
治療を始めたときに双極性障害を伝えることで、周囲の人が状況を理解し、必要なサポートを提供しやすくなります。
また、治療にともなうスケジュール変更や気分の変動があったとしても、事前に説明することで誤解を防ぎ、安心感を持って見守ってもらえるでしょう。
さらに、オープンに話すことで周囲の理解を得やすくなり、治療に専念できます。
精神科へいった方がいい症状やサインについて知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
双極性障害の伝え方

双極性障害の症状は、人によって異なります。
また、双極性障害について理解していない人も多いため、症状やサポートの仕方などを伝えるときには、工夫が必要です。
ここからは、双極性障害の伝え方を6つ紹介します。
- 自己理解を深める
- 症状だけでなくできることやサポートしてほしいことも伝える
- 伝えたいことをリスト化する
- 冷静に伝える
- 聞き手が質問しやすい雰囲気をつくる
- 治療中であることも伝える
- 専門家の意見を踏まえる
- 専門的な情報が載った資料を活用する
自己理解を深める
双極性障害について理解してもらう前に、まず自分自身が病気の特徴や自分の感情・行動パターンを理解しましょう。
自己理解が深まると、自分の状態を具体的に説明しやすくなり、周囲も状況を把握できるようになります。
また、自分のニーズやサポートの仕方を明確に伝えることで、相手もどのように接すればいいかわかり、適切なサポートを受けやすくなります。
症状だけでなくできることやサポートしてほしいことも伝える
双極性障害を周囲に理解してもらうためには、症状だけでなく、自分ができることやサポートしてほしいことも伝えましょう。
症状のみを伝えると、周囲に誤解や不安を与える可能性があります。
自分の強みや取り組めることを共有することで、前向きな印象を与えられるでしょう。
また、具体的なサポート方法を伝えると、周囲もどう行動すべきか理解しやすくなり、効果的な支援を受けられます。
双極性障害をはじめとした精神障がいを持つ人との接し方について詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
伝えたいことをリスト化する
伝えたいことをリスト化することで、双極性障害について理解してもらいやすくなります。
伝えたいことをリスト化すると、具体的な症状、サポートの要望、困難な場面などを整理しやすくなります。
また、自分自身の状況を冷静に見つめ直す機会にもなり、伝えるべきポイントを優先順位付けしやすくなります。
冷静に伝える
双極性障害について理解してもらう際に冷静に伝えることで、相手が話の内容を正確に受け止めやすくなり、誤解や偏見を防げます。
感情的になると、伝えたい内容が曖昧になったり、相手が圧倒されてしまいます。
一方で、冷静に伝えることにより、具体的な症状やサポートの要望などを論理的に説明でき、相手も共感しやすくなるでしょう。
また、冷静な態度は自分が状況をしっかり把握しているという印象を与え、信頼感を高める効果もあります。
聞き手が質問しやすい雰囲気をつくる
双極性障害について理解を深めてもらうために、聞き手が気軽に質問できる雰囲気をつくりましょう。
質問しやすい環境を提供することで、相手が自分の疑問や不安を解消しやすくなり、より正確に理解してもらえます。
また、対話を通じて双方のコミュニケーションが深まり、信頼関係の構築にも役立ちます。
緊張感のある場では相手が遠慮し、誤解が生じる可能性がありますが、リラックスした雰囲気であれば、オープンで誠実な対話が可能になるでしょう。
治療中であることも伝える
双極性障害について理解してもらう際に、治療中であることを伝えましょう。
治療を受けていることを伝えることで、病気への対処に前向きに取り組んでいる姿勢を示せます。
これにより、相手が状況をより安心して受け止めやすくなり、偏見や誤解を減らせるでしょう。
また、治療プロセスを共有することで、サポートを受ける際の具体的な方法についても話し合いやすくなり、周囲からの適切な理解と支援を得られます。
専門家の意見を踏まえる
専門家の意見を踏まえることは、双極性障害について理解を深めてもらうために効果的です。
専門家の診断や説明を共有することで、病気の本質や治療の必要性を科学的根拠にもとづいて伝えられるため、誤解や偏見を防げます。
無料相談を受け付けている専門機関もあるので、気になる方は利用してみてください。
専門的な情報が載った資料を活用する
専門的な情報が載った資料を用いることは、情報の信頼性と正確性を担保するために有効です。
資料には、病気の症状や治療法、一般的な対処法が網羅されています。
言語化しにくいことも、資料があれば簡単に補足できるでしょう。
また、視覚的に整理された情報は、聞き手にとって理解しやすく、誤解を減らせます。
双極性障害について理解がある人と出会いたい方にはIRODORI

今回は、双極性障害を周りに伝えるべきかどうかの判断基準と、周りの人へ双極性障害のことを打ち明けるときの伝え方を紹介しました。
双極性障害は、性別や年齢問わず発症の恐れがある精神障がいです。
突然発症したとしても冷静に対応できるように、今の内から双極性障害への理解を深めましょう。
また、双極性障害のことを打ち明けられる友人やパートナーと出会いたい方には、障害者の出会いを応援するマッチングアプリ『IRODORI』がおすすめです。
障がい者と障がいに理解がある方のみが在籍しているIRODORIは、年齢や移住地など多彩な条件でユーザー検索できるため、自分にぴったりの友人やパートナーを探せます。
また、グループチャットなどもできるため、障がい者向けコミュニティを形成したい方にもおすすめです。
興味がある方は、カンタン無料登録で今すぐはじめてみてください!