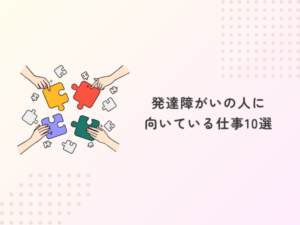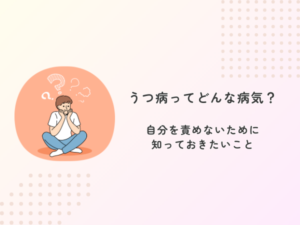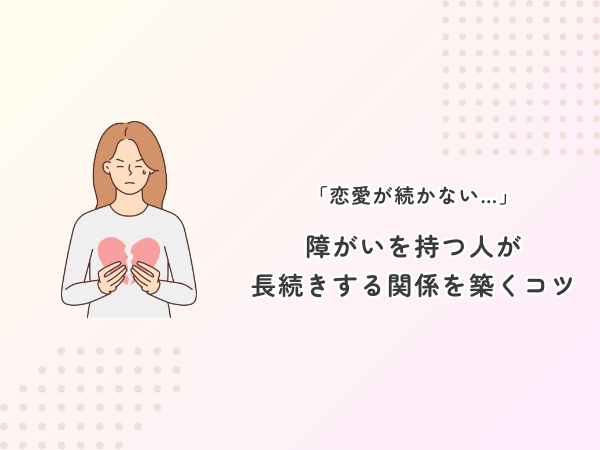
障がいを持つ人は、自身の障がいだけでなく、社会的要因などの影響で恋愛が長続きしないことがあります。
その一方で、障がいを持っていたとしても、パートナーと良好な関係を築けている方もいます。
なぜ、障がいを持っていたとしても恋愛が長続きする人としない人がいるのでしょうか?
本コラムでは、障がいを持つ人が長続きする関係を築くコツを紹介します。
Contents
障がいを持つ人の恋愛が長続きしない理由

ここからは、障がいを持つ人の恋愛が長続きしない理由を6つ紹介します。
- コミュニケーションが難しい
- 依存や過度な期待がある
- 社会的な偏見や誤解がある
- 自己肯定感が低い
- パートナーと価値観が異なる
- パートナーの負担が大きくなる
コミュニケーションが難しい
障がいを持つ人が恋愛を長続きさせることが難しいとされる理由のひとつが、コミュニケーションに課題があることです。
障がいを持っていると、障がいに起因する誤解や伝え方の違いから、気持ちがうまく伝わらず、関係にすれ違いが生じることがあります。
とくに、発達障がいや統合失調症などの精神障がいは、コミュニケーションへの影響が顕著に見られます。
発達障がいや統合失調症について詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
依存や過度な期待がある
障がいを持つ人が恋愛を長続きさせることが難しいとされる理由のひとつに、パートナーへの依存や過度な期待があります。
障がいによる不安から、パートナーに精神的な支えを求めすぎることで、関係のバランスが崩れ、相手に負担を感じさせてしまうことがあります。
とくに、不安障がいなどの精神障がいを持っていると、依存や過度な期待が現れやすいでしょう。
不安障がいについて詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
社会的な偏見や誤解がある
障がいを持つ人が恋愛を長続きさせることが難しいとされる背景には、社会的な偏見や誤解があります。
障がいに対する正しい理解が不足していると、周囲からの否定的な視線や無理解がストレスとなり、関係に影響を与えるでしょう。
とくに、普段から障がいを持つ人との接触頻度が少ないと、誤解や偏見を持ちやすくなります。
自己肯定感が低い
障がいを持つ人は、周囲との違いを意識することで自己肯定感が低くなりやすく、それが恋愛関係に影響を与えることがあります。
具体的には、自信のなさから相手に過度に依存したり、愛情を素直に受け取れなかったりすることが原因で関係が不安定になります。
とくに、うつ病や発達障がいなどを持つと、自己肯定感が下がりやすくなるでしょう。
うつ病について詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
パートナーと価値観が異なる
障がいを持つ人は、生活環境や経験の違いからパートナーと価値観が異なることがあります。
一例として、障がいに対する理解不足や意志疎通できないことによるすれ違いなどが生じます。
わずかな差異だとしても、恋愛関係に影響を与えることがあるでしょう。
パートナーの負担が大きくなる
障がいを持つ人が生活するためには、周囲のサポートが欠かせません。
具体的には、移動支援や日常生活の援助、医療サポート、就労支援などが求められます。
サポートによりパートナーに精神的・身体的な負担が積み重なることで、関係に疲れやすれ違いが生じ、恋愛が長続きしなくなります。
長続きする関係を築くコツ

ここからは、障がいを持つ人がパートナーとの関係性を長続きさせるコツを5つ紹介します。
- 自己理解を深める
- 自分の気持ちや悩みを素直に伝える
- 適度な距離を維持する
- 衝動的な言動を避ける
- 専門家のサポートを活用する
自己理解を深める
障がいを持つ人が自己理解を深めることは、恋愛関係を長続きさせるうえで欠かせません。
自分の特性や困難を正しく理解し、どのようなサポートが必要かをパートナーに適切に伝えることで、誤解やすれ違いを減らせます。
また、自分の強みや価値を理解することで、自己肯定感が高まり、より安定した関係を築けます。
自分の気持ちや悩みを素直に伝える
障がいを持つ人が自分の気持ちや悩みを素直に伝えることは、恋愛関係を長続きさせるのに有効です。
相手に本音を伝えることで、誤解を防ぎ、共感や理解を得やすくなります。
また、悩みを共有することでパートナーとの信頼関係が深まり、支え合える関係を築けます。
適度な距離を維持する
障がいを持つ人が恋愛関係を長続きさせるには、パートナーと適度な距離を保ちましょう。
お互いに依存しすぎると、精神的負担が生じやすく、関係が不安定になります。
適切な距離を保つことで、相手を尊重しつつ自分の心身のバランスも整えやすくなります。
衝動的な言動を避ける
障がいを持つ人が恋愛関係を長続きさせるには、衝動的な言動を避けましょう。
感情が高ぶったときにすぐ反応すると、誤解や対立を招きやすく、関係が不安定になることがあります。
気持ちが揺れたとしても、少し時間をおいて一度落ち着き、冷静に自分の思いを伝えましょう。
専門家のサポートを活用する
専門家のサポートを活用することは、障がいを持つ人が恋愛関係を長続きさせるために有効です。
心理カウンセラーや恋愛相談の専門家に相談することで、自己理解が深まり、感情や行動のコントロールがしやすくなります。
また、早い時期からサポートを受けることで、関係を健全に保ちつつ、パートナーと一緒に成長できる環境をつくれます。
障がいを持つ人のパートナーが意識すべきこと

ここからは、障がいを持つ人ではなく、パートナーが意識すべきことを4つ紹介します。
- 共感する姿勢を示す
- サポートを無理強いしない
- 柔軟に対応する
- パートナー自身のケアも忘れない
共感する姿勢を示す
障がいを持つ人は、日常生活や対人関係で特有の困難に直面することがあります。
パートナーが共感する姿勢を示すことで、相手は安心感を得られ、心を開きやすくなります。
また、共感は理解を深めるだけでなく、信頼関係を築く基盤となり、誤解や不安を軽減するでしょう。
お互いの立場を尊重し合い、安定した関係を築いてください。
サポートを無理強いしない
障がいを持つ人をサポートするときは、本人の意志を尊重しましょう。
過剰な手助けや無理強いは、自立心を損なわせたり、無力感を抱かせたりします。
必要な時に寄り添い、相手のペースに合わせた支援を心がけることで、信頼関係が深まります。
柔軟に対応する
障がいを持つ人の状況や体調は日によって変化することがあり、一律の対応では十分なサポートが難しいでしょう。
パートナーが柔軟に対応することで、相手の負担を軽減し、安心して過ごせる関係を築けます。
また、相手の気持ちやニーズに寄り添いながら接することで、信頼関係が深まり、良好な信頼関係を育めます。
パートナー自身のケアも忘れない
障がいを持つ人を支えるパートナーは、相手を気遣うあまり自身の心身の健康を後回しにする傾向があります。
しかし、パートナー自身が心身ともに健やかでないと、安定したサポートと良好な関係を保てません。
自分をケアすることで、心の余裕が生まれ、相手に対しても思いやりを持った対応ができるようになります。
障がいを持つ人の悩みを相談できる専門機関
障がいを持つ人のなかで、自分の力だけではどうしようもできない悩みを抱えている方には、専門機関への相談がおすすめです。
ここからは、障がいを持つ人の悩みを相談できる専門機関を5つ紹介します。
- 身体(知的)障害者更生相談所
- 精神保健福祉センター
- 市町村福祉事務所
- 障害者総合支援センター
- 障害者福祉センター
身体(知的)障害者更生相談所
身体(知的)障害者更生相談所は、身体や知的障がいを持つ人やその家族を支援する専門機関です。
障がいのある人が自立した生活を送れるよう、医師や心理士、ソーシャルワーカーなどがカウンセリングを通じてリハビリや就労支援、福祉サービスの利用に関するアドバイスを提供します。
身体や知的障がいに関する生活・就労・福祉サービスの悩みを抱えている人は利用してみてください。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、心の健康に関する相談や支援を受け付けている公的機関です。
精神疾患を抱える人やその家族に対し、専門のカウンセリングやリハビリ支援、医療機関との連携、地域での生活支援などを提供します。
また、精神保健に関する普及啓発活動や、自殺予防、アルコール依存などの問題に対する相談も受け付けており、地域における心の健康づくりをサポートする役割を担っています。
心の健康や精神的な不安、生活上の悩みを抱えている人は利用してみてください。
市町村福祉事務所
市町村福祉事務所は、地域住民の生活を支援するために設置された公的な福祉機関です。
生活困窮者への生活保護の相談・支援、障がい者や高齢者、子どもに関する福祉サービスの窓口として機能しています。
一例として、介護や育児支援や経済的困難に直面している人への相談対応、必要な福祉制度の案内や手続きのサポートなどを担当しています。
生活支援や福祉サービスの利用、経済的な悩みを抱えている人は利用してみてください。
障害者総合支援センター
障害者総合支援センターは、障がいを持つ人やその家族が生活や就労に関する支援を受けられる公的な相談窓口です。
福祉や医療、就労、教育などの分野で必要なサービスをつなぐ役割を果たします。
専門の相談員が個々の状況に応じた支援計画を立て、適切な福祉サービスや地域資源を活用できるようサポートすることで、障がい者が自立した生活を送れるよう支援します。
障がい者福祉センターは、生活全般や社会参加に関する悩みを持つ人は利用してみてください。
障害者福祉センター
障害者福祉センターは、障がいを持つ人やその家族が生活や就労に関する相談や支援を受けられる施設です。
生活支援や就労支援、リハビリテーション、社会参加促進など、幅広い福祉サービスを提供します。
また、各種福祉制度の案内や地域の関連機関と連携し、利用者が自立した生活を送れるようサポートを提供しています。
生活、就労、福祉サービスの利用など、幅広い支援を求めている人は利用してみてください。
障がいがあっても長続きする関係を築きたい方にはIRODORIがおすすめ

今回は、障がいを持つ人が長続きする関係を築くコツを紹介しました。
障がいを持つ人が長続きする関係を築くためには、相互理解と支え合いが重要です。
自己理解を深めつつ、コミュニケーションを大切にすることで、パートナーと共に困難を乗り越えられます。
障がいについてどのように伝えればいいかわからない方は、精神科医やカウンセラーなどの専門家に相談してください。
自身の障がいについて理解してくれるパートナーと出会いたい方には、障害者の出会いを応援するマッチングアプリ『IRODORI』がおすすめです。
IRODORIは、障がいを持つ方とその理解者が利用できる友活・恋活・婚活アプリです。
趣味や関心事を共有するコミュニティで交流したり、マッチング機能を通じて理想のパートナーを探したりできます。
また、シークレットモードなどのプライバシー保護機能も備えているため、身バレを気にせずに利用できます。
さらに、IRODORIでは、「同じ障害の悩みを持つ人と話したい」「文章を書くのが少し苦手」といったご利用者さまの声にお応えして、もっと「仲間」が見つかりやすく、もっと「使いやすい」アプリになるよう、新機能を準備中です。
ADHDやASDなど、同じ障害特性を持つ方とのマッチング機能や、自己紹介文の作成サポート機能など、皆様の声を反映した新機能の追加を予定しています。
興味がある方は、カンタン無料登録で今すぐはじめてみてください!