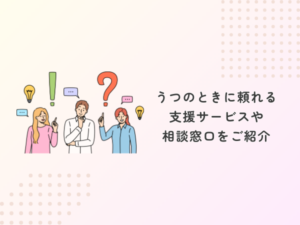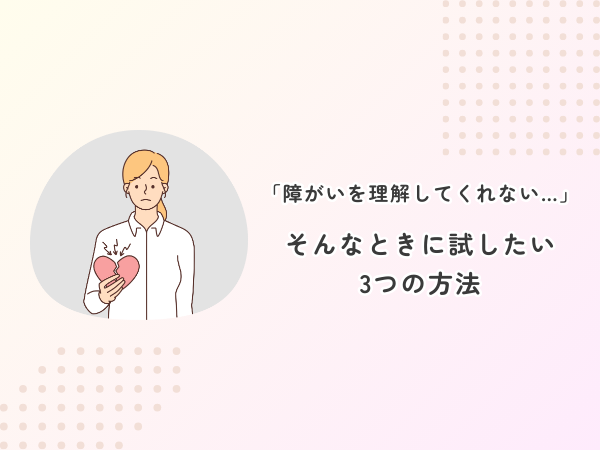
自身の障がいと向き合うためには、周囲のサポートが欠かせません。
障がいを持っている方で、周囲の人が自身の障がいを理解してくれないと感じた経験のある方は少なくないでしょう。
そこで、本コラムでは周囲の人が自分の障がいについて理解してくれないときに試してほしい3つの方法について解説します。
Contents
障がいについて周囲が理解できない理由

周囲に自身の症状を伝えたとしても、うまく伝わらないことがあります。
ここからは、障がいについて周囲が理解できない理由を5つ紹介します。
- 障がいに関する知識不足
- 目に見えない障がいがある
- 人によって症状が異なる
- メディアや社会的なステレオタイプに基づく偏見がある
- 障がい者との接触機会が少ない
障がいに関する知識不足
内閣府が実施した障害者に関する世論調査では、障がいがある人に対して差別や偏見があると思うまたは、ある程度はあると思うと回答した人の割合は、88.5%でした。
障がいに関する知識が不足していることは、周囲が障がいを正しく認識できない大きな要因です。
障がいに対する具体的な情報が伝わっていないことで、サポートの方法がわからず、関わり方に戸惑うこともあります。
障がいの代表例である精神障がいへの理解を深めたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
目に見えない障がいがある
発達障がいや高次脳機能障がい、内部障がいなどは、症状が目に見えません。
外見から判断できないと、周囲から理解されにくく、誤解を生みます。
また、外見で判断できないと、障がいへの理解を求めても軽視されることもあります。
人によって症状が異なる
障がいは、同じ診断名でも人によって症状の現れ方や程度が異なるため、周囲が理解しにくいことがあります。
ある人にはできることが、別の人には困難な場合もあり、その差が誤解を生みます。
また、日によって体調や症状が変化することも理解を難しくする要因のひとつです。
メディアや社会的なステレオタイプに基づく偏見がある
特定の視点や意見を強調し、他の視点を無視または軽視する報道のことをメディアバイアスといいます。
メディアバイアスや社会的なステレオタイプに基づく偏見は、障がいに対する誤ったイメージを生み出し、正しい理解を妨げる要因のひとつです。
一例として、障がいを「弱さ」や「無力さ」と結びつける表現は、実際の個々の能力や特性を見極めづらくします。
障がい者との接触機会が少ない
障がい者との接触機会が少ないと、実際の生活や困難について理解する機会が限られ、誤解や偏見が生まれやすくなります。
直接的な交流がないと、障がいに関する知識はメディアや噂に依存するため、実態と異なる印象を持つこともあります。
周囲の人に自身の障がいを理解してもらえないときに試してほしいこと

ここからは、周囲の人に自身の障がいを理解してもらえないときに実践してほしいことを3つ紹介します。
- 自分の特性や必要な配慮を具体的に伝える
- コミュニケーション方法を工夫する
- 専門機関や支援団体に相談する
自分の特性や必要な配慮を具体的に伝える
自身の障がいについて話すときは、自身の特性や必要な配慮を具体的に伝えましょう。
障がいは個人によって症状や影響が異なります。
障がいを持つ人のことを理解するためには、一般的な理解だけでは不十分です。
具体的な説明により、相手はどのように接するべきかを理解しやすくなり、共に快適な環境を築けるようになります。
コミュニケーション方法を工夫する
自身の障がいについて理解してもらえないときは、コミュニケーション方法を工夫しましょう。
相手の理解度に応じて言葉を選んだり、例を挙げたりすることで、抽象的な説明では伝わりにくい部分を補えます。
また、文章や図を用いるなど、複数の手段を活用することで、相手にとって理解しやすい形で情報を伝えられます。
専門機関や支援団体に相談する
自身の障がいについて周囲に理解してもらえないときは、専門機関や支援団体に相談しましょう。
専門機関や支援団体に相談すると、専門的な知識を持つ相談員が状況に応じた適切なアドバイスを提供し、どのように周囲に伝えるべきか具体的な方法を教えてくれます。
また、第三者の意見やサポートが加わることで、相手に対して客観的かつ説得力のある説明が期待できます。
専門機関や支援団体に協力してもらうことが難しい場合は、友人や家族など信頼できる人を頼りましょう。
どのような機関が障がいの相談を受け付けているか知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
うつのときに頼れる支援サービスや相談窓口をご紹介 | 障がい者の友活・恋活・婚活アプリ「IRODORI」
障がいについて理解してもらえないときのセルフケア

自身の障がいについて理解が得られないと、ストレスを感じることがあります。
そこで、ここからは障がいについて理解してもらえないときに実践してほしいセルフケアを5つ紹介します。
- 信頼できる友人や家族と話す
- リラクゼーション法を取り入れる
- 趣味や好きなことに没頭する
- 適度に運動する
- 十分な睡眠を確保する
信頼できる友人や家族と話す
障がいについて理解してもらえないときは、信頼できる友人や家族と話しましょう。
身近な人に悩みを打ち明けることで、自分の気持ちを整理できるだけでなく、客観的な視点からアドバイスをもらえます。
また、自身の症状を伝える場に立ち会ってもらうことで、周囲の人がスムーズに理解できるようになります。
リラクゼーション法を取り入れる
障がいについて理解してもらえないときは、リラクゼーション法を取り入れましょう。
障がいについて理解してもらえない状況が続くと、精神的なストレスや不安が蓄積されやすくなります。
リラクゼーション法を取り入れることで、心身の緊張をほぐし、気持ちを落ち着かせられます。
とくに、深呼吸やストレッチ、瞑想などは、自分の心を整え、冷静に状況を受け止める力を養う手助けとなり、前向きにコミュニケーションを続ける余裕を生み出すでしょう。
効果的なリラクゼーション法を知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
趣味や好きなことに没頭する
障がいについて理解してもらえないときは、趣味や好きなことに没頭しましょう。
障がいについて理解されない状況が続くと、自己肯定感が低下し、心が疲弊しやすくなります。
趣味や好きなことに没頭することで、心に安らぎと充実感を得られます。
楽しい時間を過ごすことで、気持ちをリフレッシュし、ネガティブな感情に振り回されないようにしましょう。
適度に運動する
障がいについて理解してもらえないときは、適度に運動しましょう。
障がいについて理解されない状況が続くと、ストレスが蓄積し、心身に悪影響を及ぼすことがあります。
適度な運動は、ストレスホルモンを減少させ、気分を安定させる効果があるセロトニンの分泌を促します。
さらに、身体を動かすことで血行がよくなるため、心身をリフレッシュできるでしょう。
心を落ち着かせ、前向きな気持ちを取り戻すためにも運動は効果的です。
十分な睡眠を確保する
障がいについて理解してもらえないときは、十分な睡眠を確保しましょう。
障がいについて理解されない状況が続くと、精神的なストレスが蓄積し、心身のバランスが崩れやすくなります。
十分な睡眠を確保することで、脳と身体がしっかり休まり、ストレスに対する耐性が高まります。
また、睡眠は感情を安定させるホルモンの分泌を促すため、ネガティブな思考を和らげられるでしょう。
心身の健康を保ち、前向きな気持ちを取り戻すためにも質の良い睡眠は効果的です。
自身の障がいについて理解してくれる人と出会いたい方にはIRODORIがおすすめ

今回は、周囲の人が自分の障がいについて理解してくれないときに試してほしい3つの方法について解説しました。
周囲の人が自分の障がいについて理解することは、コミュニケーションの円滑化や支援を得るために欠かせません。
自分の力だけでは上手く伝えられないという方は、カウンセラーや精神科医など、専門家の協力を求めてください。
伝え方をはじめ、障がいの悩みを気軽に相談できる友人やパートナーを探している方には、障害者の出会いを応援するマッチングアプリ『IRODORI』がおすすめです。
障がいを持つ人と障がいに理解がある人のみが在籍しているIRODORIは、障がいについて寛容的なユーザーが多いため、自身の障がいや悩みについて気軽に話せます。
また、グループ通話機能「LIVE」を利用すると、複数のユーザーと同時にコミュニケーションを取れます。
さらに、IRODORIでは、「同じ障害の悩みを持つ人と話したい」「文章を書くのが少し苦手」といったご利用者さまの声にお応えして、もっと「仲間」が見つかりやすく、もっと「使いやすい」アプリになるよう、新機能を準備中です。
ADHDやASDなど、同じ障害特性を持つ方とのマッチング機能や、自己紹介文の作成サポート機能など、皆様の声を反映した新機能の追加を予定しています。
興味がある方は、カンタン無料登録で今すぐはじめてみてください!